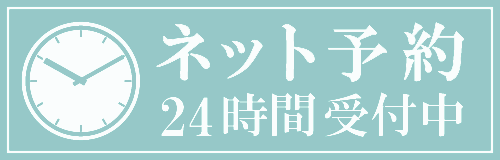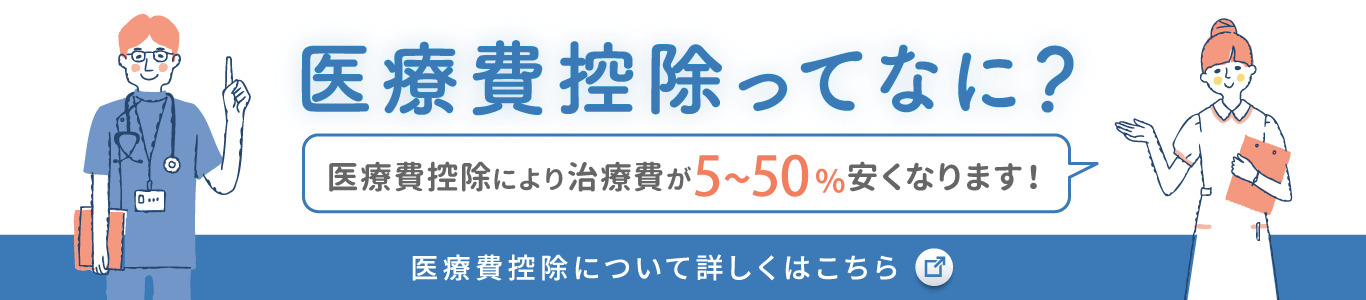こんにちは!
中延昭和通り歯科の歯科衛生士てす。
今回は入れ歯が合わなくなる理由についてお話していきます。

入れ歯を作ったばかりの頃はピッタリ合っていても、時間が経つと違和感を感じたり、ズレたりすることがあります。
これは、さまざまな理由で入れ歯とお口の形が合わなくなってしまうためです。
ここでは、入れ歯が合わなくなる主な原因をご紹介します。
1. 顎の骨や歯ぐきの変化
歯を失うと、顎の骨や歯ぐきは少しずつ痩せていきます。これにより、入れ歯とお口の形が合わなくなり、ズレや痛みの原因になります。
2. 入れ歯の摩耗や変形
長く使っていると、入れ歯自体がすり減ったり、変形したりすることがあります。特に人工の歯の部分が摩耗すると、噛み合わせが変わり、違和感を感じやすくなります。
3. 体重の変化
急激な体重の増減は、歯ぐきの厚みにも影響を与えます。特に体重が減ると歯ぐきが痩せて、入れ歯が緩くなることがあります。
4. 生活習慣の変化
食生活や姿勢、噛み方の癖などが変わると、入れ歯にかかる力のバランスが崩れ、合わなくなることがあります。
5. 入れ歯の管理不足
入れ歯の変形や劣化を防ぐためには、適切なケアが必要です。熱湯消毒や乾燥など、誤った方法でお手入れすると、入れ歯が変形し、フィット感が悪くなることがあります。
入れ歯が合わないと感じたら?
入れ歯がズレたり痛みを感じたりする場合は、放置せずに歯科医院で調整しましょう。
無理に使い続けると、歯ぐきに傷がついたり、噛み合わせが悪くなったりする可能性があります。
定期的なチェックと調整を行い、快適に入れ歯を使い続けましょう!
日付: 2025年6月30日 カテゴリ:スタッフ体験記録